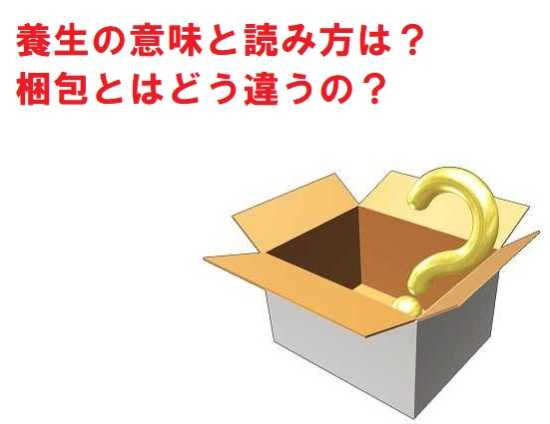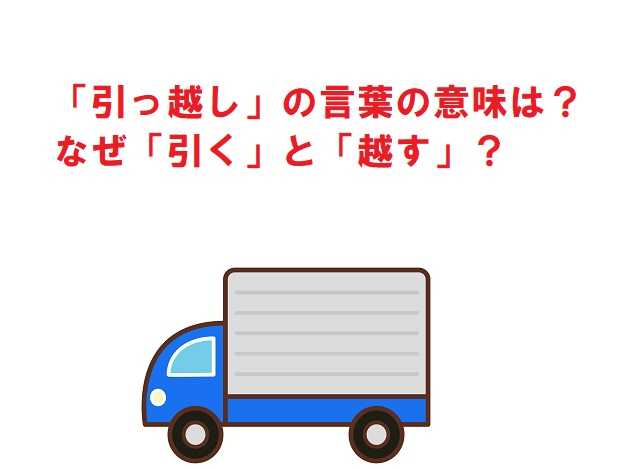
私たちが普段使っている「引っ越し」と言う言葉。
何気なく使っていますが、よく考えると不思議です。
この言葉には「引く」と「越す」という2つの漢字が使われています。
「最近こちらに越してきました」
というように「越す」だけでも分かるのですが、「引く」という文字も入っています。
移動するのになぜこの字が使われるのでしょうか。今回は引っ越しという言葉の意味について解説します。
言葉の意味は?なぜ「引く」と「越す」?
「引く」には、基本的には「物を手前に近づける」という意味があります。
「引く」には使い方がたくさんあって、
「網を引く」「カーテンを引く」「くじを引く」「馬が荷物を引く」「電話を引く」「人目を引く」「辞書を引く」「弓を引く」
等たくさんあります。
一方「越す」は、「手前から向こうに移るために、ある場所を通りすぎて向こう側に行く」という意味があります。
使い方としては、
「山を越す」「冬を越す」「隣県に越す」
山や冬など、多少困難を感じるものを通過する時に「越す」は使われていましたが、転じて「隣県に越す」というように単に移動するだけでも「越す」という言葉は使われるようになりました。
ですから「越す」には、それだけで「引っ越しする」という意味があります。
分かりにくいのは「引く」ですよね。
手前に近づける意味があるのに、「○○県の方に引っ越します」というように、向こう側に行く場合にも使いますよね。
これは、「引く」には、引く動作によってその場にあるものをどこか別の場所へ移動させる、という意味があるからです。
先ほど紹介した「馬が荷物を引く」がこれに当たります。
昔は荷物や人を馬に乗せて運んでいました。馬を引いて荷物を運んでいたのです。

荷物を載せた馬を引いて山を越えて別の地の移り住む、そこから「引っ越す」という言葉が使われているのですね。
「引っ越し」はいつから使われた言葉?

この言葉がいつから使われたのかは明らかになっていません。
ですが、馬を引いていた時代ですから相当古いことが分かります。
また、引っ越しの動詞は「引き越す」ですが、この言葉は古語辞典にも載っています。
枕草子 細殿の遣戸を
「纓(えい)をひきこして顔を塞(ふた)ぎて」
[訳] 纓(=冠の後ろに垂らした薄絹)を(肩越しに)前へまわして顔を隠して。出典:weblio古語辞典
枕草子は平安時代の作品です。その時代にはもう「引き越す」という言葉は使われていたんです。
あと「引越蕎麦」という言葉を聞いたことがあるでしょう。
引っ越しのお供とも呼べる「引越蕎麦」が流行し始めたのは江戸時代からと言われています。
ちなみに引越蕎麦が生まれた由来ですが、「蕎麦」だけに「おそば」。
言葉遊びが盛んに行われていた江戸時代で「これからおそば(蕎麦)で末永くよろしくお願いいたします」
と言う意味でご近所に配っていたと言われていますよ。
今では廃れつつある引っ越し蕎麦ですが、江戸時代からあった伝統的な風習だと思うと少し廃れるのがもったいない気がしてきますよね。
守っていきたい風習の1つです。
まとめ
今回は引っ越しという言葉の意味について紹介しました。「越す」には「引っ越す」という意味がすでにあって、「引く」は「荷物を引く」という意味です。
それが合わさった言葉です。
引っ越しという言葉はいつから使われているのかはっきりしていません。
しかし、引き越すという言葉は平安時代からありましたし、引っ越しのお供ともいえる引っ越し蕎麦は江戸時代から使われてきたという言葉です。相当古いことが分かりますね。
参考にしてください。(おわり)